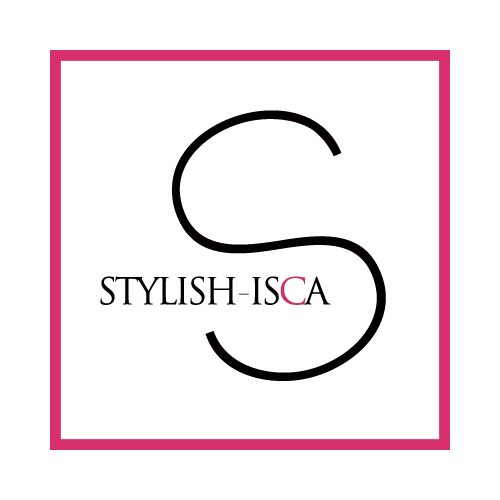※長い文章を読むのが大変な方は音声での語りでお聞きください。
2023年2月14日(火)〜2023年4月9日(日)文化村ミュージアム開催のマリーローランサンとモード展に行ってきました。
ふたつの世界大戦に挟まれた1920年代のパリ。それは様々な才能がジャンルを超えて交錯し、類まれな果実を生み出した、奇跡のような空間でした。とりわけ女性たちの活躍には、目を見張るものがありましたが、ともに1883年に生まれたマリー・ローランサンとココ・シャネルの二人は、大戦後の自由な時代を生きる女性たちの代表ともいえる存在でした。
女性的な美をひたすら追求したローランサンと、男性服の素材やスポーツウェアを女性服に取り入れたシャネル。本展では美術とファッションの境界を交差するように生きた二人の活躍を軸に、ポール・ポワレ、ジャン・コクトー、マン・レイ、そして美しいバイアスカットを駆使したマドレーヌ・ヴィオネなど、時代を彩った人々との関係にも触れながら、モダンとクラシックが絶妙に融合する両大戦間パリの芸術界を俯瞰します。
時代とともにありながら、時代を超えた存在となったローランサンとシャネル。二人の創作の今日的な意味とその真価が、生誕140年を記念するこの展覧会で明らかになるでしょう。
マリーローランサンが描いたシャネルの自画像は強い女性シャネルを少し悩む女性として描かれているように感じました。出来栄えに満足が出来ず受取を拒否したという逸話が残っています。この自画像をシャネルはどう感じたのでしょうか?儚げなシャネルも素敵ですが、自分の思う自分とのギャップがあったのでしょうか。そんなことを感じたのも正直な気持ちでした。
写真を写して良いモノは撮らせていただきました。(以下展示品からご紹介します)




1883年マリー・ローランサンはパリ生まれ。アカデミー・アンベールで絵画を学ぶ。ピカソやブラックとの交流から、初期にはキュビスムの影響色濃い作風であったが、後に、パステル調の淡い色調と優美なフォルムが特徴の女性的な作風に。エコール・ド・パリの中でもひときわ輝く存在となる。詩人アポリネールとの大恋愛でも知られる。
1883年10月31日、雨の降るパリのシャブロル街に、マリー・ローランサンは生まれました。
父と母は婚姻関係を結んでおらず、マリーは私生児として、母ひとり子ひとりの家庭で育ちます。
服の仕立てで生計を立てる母ポーリーヌと、ふたりだけの静かな生活。そこに時々訪ねて来る男性、それが実の父であるアルフレッド・トゥーレでした。
マリーはこの闖入者が好きではなく、宿題をするマリーに父が「ヒツジは草食動物だ」と教えると、反発して、「ヒツジは肉食動物だ」と書いて提出したという逸話があります。
女学校での成績こそ振るわないものの読書が好きで、想像力豊かなマリーは、ある日、家具付きのアパートの窓辺でくつろぐ若い男女の姿を見かけます。
このとき、マリーは天啓に打たれたように「画家になる」と決意します
後にその思いが昇華したのがこちらの作品。家具付の貸家 1912年 油彩
画家となることに反対する母を説得するため、まずは陶磁器の絵付けの学校に通い、デッサン学校、そして絵の私塾であるアカデミー・アンベールの門をくぐります。
ここでの同窓生が、後に野獣派や立体派の担い手となるジョルジュ・ブラックでした。ブラックはいち早くマリーの才能を認め、伝説のアトリエ「洗濯船」の芸術仲間たちに紹介します。
この「洗濯船(バトーラヴォワール)」での出会いが、マリーの画家人生の大きな転機となります。
このころアトリエにいたのは、錚々たるメンバーでした。
まずは、スペイン出身のパブロ・ピカソ。彼が当時描いていた「アヴィニヨンの娘たち」は、マリーに衝撃を与えます。
「きっと歴史を変える一枚になる」と直感したマリーは、自身もいつかこんな作品を描きたいという野心を、生涯抱くことになります。
ほかには、生涯の友人となるユダヤ人詩人マックス・ジャコブ、詩人アンドレ・サルモン、画家ではアメデオ・モディリアーニ、ヴァン・ドンゲン、アンリ・マティスなども出入りしていました。アンリ・ルソーを招いてパーティーが開かれたこともあります。
ある日のこと、ピカソは、親友であるイタリア出身の詩人ギョーム・アポリネールに「君のフィアンセに会った」と、マリーを紹介します。これこそ、世紀の恋の始まりでした。
ギョームは、ピカソやブラック、ピカビア、レジェなどと並ぶ唯一の前衛女性画家としてマリーを世に紹介します。
互いの才能を認め、高め合うふたりは、モンマルトルの若い芸術家たちの憧れのカップルでした。
ギョームは後に「20世紀を連れてきた男」と称されるほど精力的な著作活動を行い、またマリーの絵も高く売れ、画家として成功を確たるものにします。
付き合っていたころ、ギョームの部屋(アパートの3階)に、マリーが得意のなわとびを飛びながら訪ねてきたという逸話があります。
ちょっと風変わりな恋人たちの幸せそうな姿が浮かんでくる、なんともかわいいエピソードです。
しかし互いの成功は、ふたりの関係に影を落とし始めます。
芸術家としての個性が時としてぶつかり合い、別れてはまた寄りを戻す、という不安定な関係が続きます。
決定打となったのは、ルーブル美術館の「モナリザ盗難事件」でした。ギョームは事件の容疑者として逮捕されてしまうのです。
スキャンダルを恐れるマリーは、もともとギョームをよく思っていなかった母の影響もあり、彼との距離を遠ざけてしまいました。
さらに、恋の終わりと時を同じくして、母ポーリーヌが病死します。
傷心したマリーはこのあと、思いもよらない選択をすることになるのですが…
この別れから生まれたのが、近代詩の金字塔となる詩「ミラボー橋」です。
後に、マリー・ローランサンと出会い、絵の弟子入りをすることになった堀口大學が、この詩を訳しています。
ミラボー橋の下をセーヌが流れ
われらの恋が流れる
わたしは思いだす
悩みのあとには楽しみがくると
日もくれよ 鐘もなれ
月日は流れ わたしは残る
(『月下の一群』より、堀口大學訳)
マリーもまた、別れを滲ませたこんな絵を描いています。
この絵の後ろに見えるのはミラボー橋。船頭の男は女を船から追い出し、女は川に沈んで行こうとしているかのように見えます。
船頭はギョームで、右側の女はマリーを表しているのです。


詩人ギョーム・アポリネールと別れたマリー・ローランサン。
伝説のカップルとして名を馳せたふたりを、なんとか修復させたいと友人たちが奔走しますが、元の恋人同士に戻ることはありませんでした。
そんなとき、マリーはパーティーでひとりの男性と出会います。ドイツから絵を学びに来ていた、オットー・フォン・ヴェッチェン男爵。
ハンサムで遊び上手なオットーは、間もなくマリーに求婚し、マリーも結婚を承諾します。
ある日、マリーはカフェでギョームにこのことを告げると、傷ついたギョームはその場を立ち去り、ふたりはこの後、二度と会うことはありませんでした。
1914年6月、パリの区役所で結婚式を挙げたマリーとオットー。しかし、このわずか6日後に、第一次世界大戦の引き金となった「サラエボ事件」が起こります。そして、ふたりの新婚旅行中、フランスとドイツの戦争が始まってしまうのです。
結婚によってドイツ国籍となったマリーは、フランスから見れば敵国人。パリに戻ることはできません。
ふたりは、中立国であるスペインに亡命する道を選びます。
しかし、スペインでも心穏やかに過ごすことはできませんでした。当局からスパイ容疑をかけられ、スペイン中を転々とすることになります。
日々の不安を打ち消すためかオットーは酒浸りになり、放っておかれたマリーは寂しさを紛らすために、たくさんの手紙や詩を書きます。
そのころ書いた詩が、有名な「鎮静剤」です。
退屈な女より もっと哀れなのは 悲しい女です。
悲しい女より もっと哀れなのは 不幸な女です。
不幸な女より もっと哀れなのは 病気の女です。
病気の女より もっと哀れなのは 捨てられた女です。
捨てられた女より もっと哀れなのは よるべない女です。
よるべない女より もっと哀れなのは 追われた女です。
追われた女より もっと哀れなのは 死んだ女です。
死んだ女より もっと哀れなのは 忘れられた女です。
(『月下の一群』より、堀口大學訳)
このころの絵画作品は、いずれもグレーの強い、憂いに沈んだ色調です。
下の「馬になった女」で描かれている自身の姿はグレー。しかし、向きあうキャンバスと心臓の色だけは薔薇色に塗られています。
この絵を描いた1918年、マリーは、マドリードで一通の電報を受け取ります。
それは、終戦の前日に、ギョームがスペイン風邪で亡くなったという知らせでした。ギョームはフランス軍に入隊し、陸軍少尉として戦いながら文学活動を続けていました。ギョームの枕元には、かつてマリーが描いた「アポリネールとその友人たち」が大切に飾られていたといいます。
馬になった女 1918年頃 油彩
戦争が終わっても、マリーとオットーの仲は修復されず、単身パリに戻ったマリーは離婚を決意します。
ひとりに戻ったパリでの生活は順調にスタートし、パリの芸術家仲間たちもマリーの帰還を歓迎しました。
また、上流階級の夫人たちから肖像画の注文が殺到し、流行画家となって地位と名声を獲得します。
このころ、マリーと同い年のひとりの女性が、やはりマリーに肖像画を依頼しています。
出来上がった肖像画を見た彼女は、自分に似ていないことを理由に、マリーに描き直しを要求しますが、マリーは怒って拒否し、作品を自分の手元に引き取ります。
この女性こそ、ココ・シャネルでした。マリーが描いたシャネルは、女性らしい儚げな雰囲気で、貧しい生まれから成功を勝ち取った“強い女”のイメージとはかけ離れていたのです。この絵はいま、パリのオランジュリー美術館で見ることができます。
ともあれ、シャネルやコレットとともに、時代の先を行く成功した女性として脚光を浴びるマリー。
しかし、その一方で、家族を持てない寂しさを、親友のニコル・グルーにも打ち明けています。
ニコルはデザイナー、ポール・ポワレの妹で、自身も帽子デザイナーでした。辛かったスペイン時代を支えた友人で、ふたりは同性愛的な関係にあったと伝えられるほど親密に付き合い、マリーが死ぬまで交流が続きます。ニコルの娘であるフロラ・グルーは、後にマリーの伝記を上梓しています。
そんなマリーのもとにやって来たのが、20歳の家政婦、シュザンヌ・モローでした。マリーは、シュザンヌを娘のように可愛がりますが、シュザンヌはマリーを慕うあまり独占欲に駆られ、自分の気に入らない客や電話は取りつがないようになりました。
母ポーリーヌとの暮らしを再現したかのような静かで穏やかな日々。しかしそこに、再び戦争―第二次世界大戦の影が忍び寄ってきます。
住みなれたアパートをドイツ軍に奪われ、終戦直後は対独協力者の容疑で逮捕され、強制収容所に収監される憂き目にも遭いました。
その収容所では、洗濯船以来の親友でユダヤ人であった詩人マックス・ジャコブが獄死しており、マリーの心にまた暗い影を落とします。
晩年は、社交界よりも修道院で過ごすことが多くなり、大好きな自宅に引きこもるようになります。
そんななかでも、創作においては、自身がこれまで使えなかった黄色を取り入れて革新を起こします。
その集大成ともいうべき作品が、下の「三人の若い女」です。
三人の若い女 1953年頃 油彩
長い間、忠実に使えてくれたシュザンヌを養女にした後、「家が大切なのは死ぬ場所だから」と言ったその言葉どおり、1956年、マリーは自宅で息を引き取ります。
ギョームからの手紙の束と赤い薔薇を胸に抱き、白いドレス姿で葬られるという、ロマンチックな死に様でした。
夢の中のようなパステルカラーから、人は彼女の作品を「甘い」「優しい」と評します。
それを、通俗的に捉え、“少女趣味”として否定的に見る人もいるのかもしれません。
しかし彼女は、まだ女性の社会的地位が低かった時代に、己の才能で成功した稀有な存在でした。
それも、名誉男性的な「強さ」によってではなく、男性に対する「コケットリー」でもなく、あくまでも「きれい」「かわいい」「エレガント」といった女性らしい価値観で勝負したところに、彼女の凄さがあるのだと思います。
戦争や恐慌が続く暗い時代のなかで、決して変節することなく描き続けられた、きれいなもの、かわいいものへの憧れ……。
その作品は、今もなお、多くの女性たちがもつ普遍的な思いに共鳴し、魅了し続けているのです。
ご紹介した作品は、「マリー・ローランサン美術館」で見られます。
◆「婦人画報」記事参照
編集・文=柏木敦子さんのをお借りいたしました。



最後のコーナーではシャネルのデザイナーをしていたカールラガフェルドのコレクションの映像と共にドレスが展示してありました。マリーローランサンとシャネルへの愛とオマージュが込められたピンクのドレスはどれも素晴らしい作品でした。
シャネルのアーティスティック・ディレクターを長年勤めたカール・ラガーフェルドが85歳で死去しましたが、この偉大なメゾンを再び世界的ブランドへと変貌させたシャネルへの貢献は素晴らしいものだったと感じました。